目次
- はじめに──“家で看取ってほしい”という言葉に思うこと
- 病とともに生きた日々──告知から闘病の5年間
- 🔹男性目線──死を覚悟した夫の心
- 支えるということ──心も体も削られていく日々
- 🔸女性目線──死を覚悟した妻の心
- 「家族の痛み」は見えにくい
- 夫の死から6年──過去を抱えながら、前を向く
- おわりに──あなたの痛みにも寄り添いたい
はじめに──“家で看取ってほしい”という言葉に思うこと
「もし癌になったら、怖いから、家族にずっとそばにいてもらって、家で最後を迎えたい」
最近、ある男性がそう語っているのを耳にしました。
その瞬間、私は思わず立ち止まり、深く考え込んでしまいました。
なぜ、それほどまでに“自分本位”になれるのだろうか──と。
それは、私自身が「家で夫を看取った」経験を持っているからです。
そしてその現実が、想像よりも遥かに過酷であったことを知っているからです。
病とともに生きた日々──告知から闘病の5年間
夫が「ステージ3の癌」と診断されたのは、今から11年前。
そこから5年間、私たちは病と向き合い続けました。
再発を繰り返し、4度の手術に耐えながら、夫は何とか命をつなごうとしていました。
「ベッドで寝ているだけでもいい。子どもの成長を見ていたい」
そう語る夫の姿に、私は何度も心を揺さぶられました。
🔹男性目線──死を覚悟した夫の心
死の影が濃くなってきたある日、夫がぽつりと呟きました。
「このまま逝くんやろか。でも、せめて家で、家族に囲まれていたい」
彼にとって“家”は安心できる場所。
愛する人たちに見守られて旅立ちたいという願いは、素直な気持ちだったのかもしれません。
でもその裏には、「支える者の現実」が見えていなかった。
死を迎える側と、支える側。そこには静かで深い隔たりがあるのです。
支えるということ──心も体も削られていく日々
夫が働けなくなると、私は昼のパートに加えて夜もアルバイト。
治療費や生活費に追われ、家計は常に崖っぷちでした。
家に一人残る夫の命が、仕事中に尽きてしまうのではと不安を抱えながらの毎日。
「もし帰宅して息をしていなかったら…」という恐怖が、常に心の中にありました。
家の空気も重く、テレビの音すら遠慮しなければならないような閉塞感。
夜のアルバイトは、ほんの少しだけ現実から逃れられる、私の「逃げ場」でした。
🔸女性目線──死を覚悟した妻の心
もし私が癌になったら──
私は「家ではなく、病院で最期を迎えたい」と思います。
誰かに大きな負担をかけてまで家で死にたいとは、私は言えない。
支える人の生活や心まで壊してしまうかもしれないことを、私は知っているからです。
私は早くから緩和ケアに入り、痛みを抑えながら静かに旅立ちたい。
それが私なりの、覚悟ある最期のかたちです。
「家族の痛み」は見えにくい
夫の苦しみを、私は誰よりもそばで見てきました。
でも、私の苦しみは誰にも見えていなかった気がします。
制度の利用を勧めても拒否され、精神的にも張り詰めた日々。
ときには、その頑なさにモラルハラスメントすら感じることもありました。
「患者の痛み」は語られても、「支える家族の痛み」は、語られにくいのが現実です。
夫の死から6年──過去を抱えながら、前を向く
夫が亡くなって、今年で7年目を迎えます。
時間が経っても、あの記憶は消えることはありません。
けれど今の私は、その記憶を「楽しいこと」で少しずつ上書きしようとしています。
前向きに、明るく、新しい思い出を重ねながら、心を癒しています。
おわりに──あなたの痛みにも寄り添いたい
介護や看取りを経験した方へ、そして今まさに支えている方へ。
あなたの疲れや痛みは、誰かがわかってくれるものです。
すべてを抱え込まなくていい。
泣きたいときには泣いてください。
あなた自身の心も、守ってあげてください。
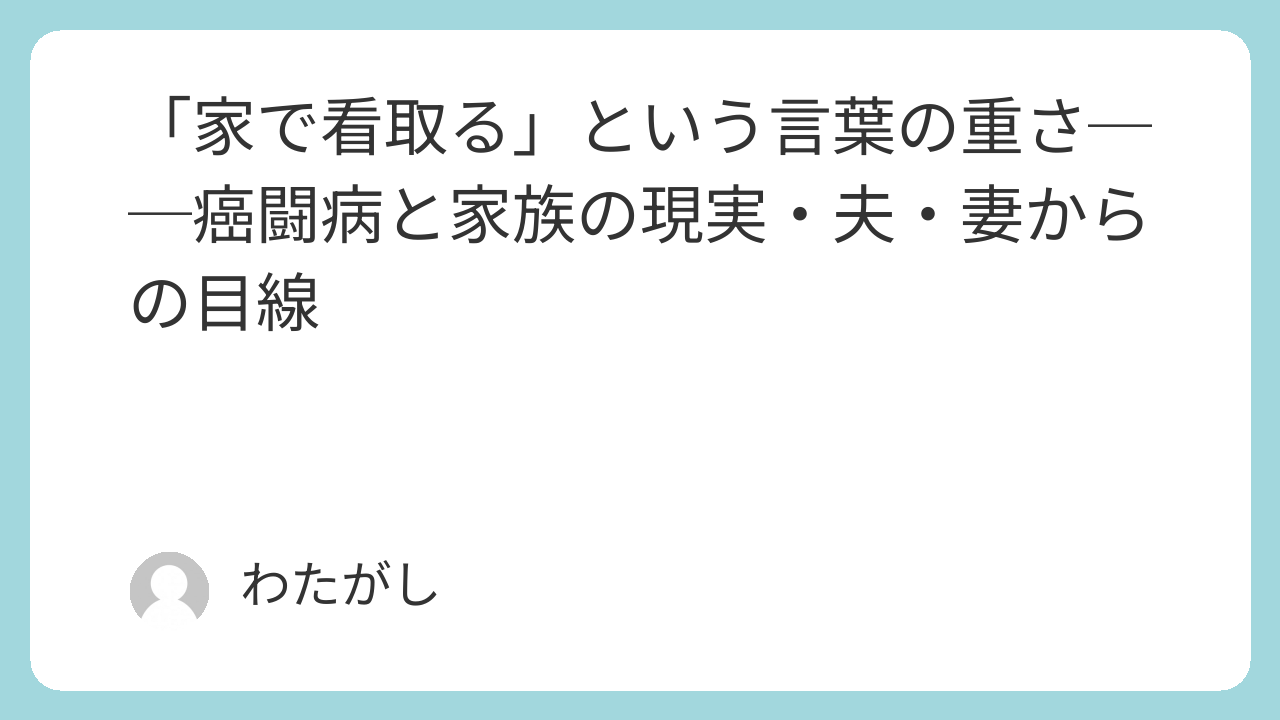
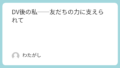
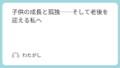
コメント